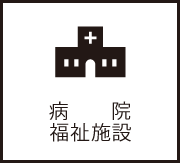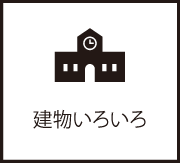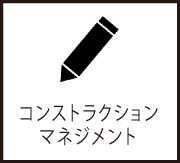最近の病院づくりで気になること
2024年7月
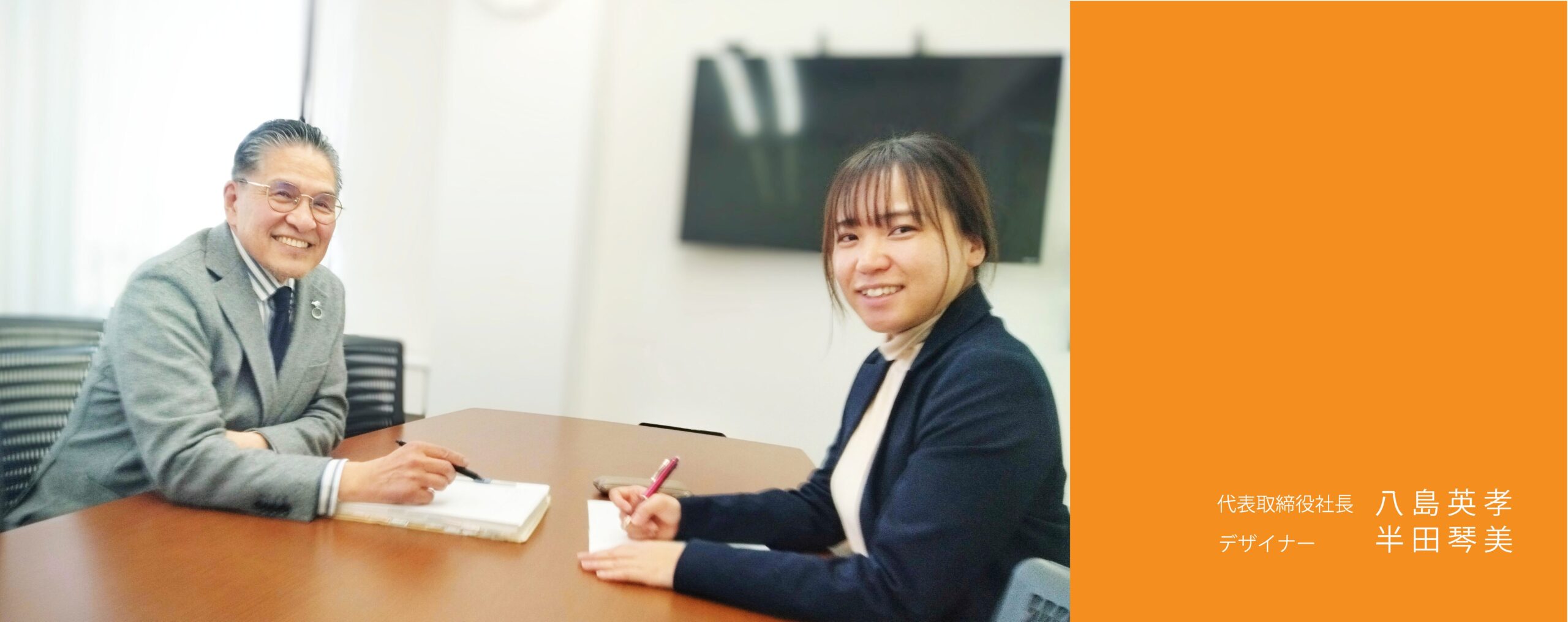 志賀設計では、既存の医療施設からいろいろなご相談を受けています。地球環境の「煮沸化」、アフターコロナという時代の中で、最近気になることを紹介しながら、病院づくりのノウハウを取り上げてみます。
志賀設計では、既存の医療施設からいろいろなご相談を受けています。地球環境の「煮沸化」、アフターコロナという時代の中で、最近気になることを紹介しながら、病院づくりのノウハウを取り上げてみます。
結露対策はこれからの病院づくりには必須
 天井面に発生した結露による水滴
天井面に発生した結露による水滴
八島:まず一番に挙げるのは、近年の高温多湿化による結露の問題です。年号が令和に変わった頃から、この問題が顕著化してきました。
半田:やはり夏場ですか?発生するのは窓ガラスなどでしょうか?
八島:発生時期はやはり夏場で、湿度と温度が上がりだす6月から9月にかけては要注意です。発生する場所ですが、最近の窓ガラスは2重ガラスになっているのが一般的なので、窓ガラスでの結露はあまり問題にはなりません。問題になるのは、天井裏とか、倉庫の中とか、空気が澱みやすい場所、普段あまり目に入らない場所で発生する結露です。
半田:そんなところが結露するんですか。
八島:天井裏は、特に要注意です。天井から水が落ちてきたので、配管などの漏水かと思って天井に入ってみると、天井板の上に水が溜まっていたという事故が確認されています。雨が漏るような場所ではないので、最初は判らなかったのですが、調べるうちに結露が原因だと判明しました。
半田:放っておくと、カビが生えてくるのではないですか?
八島:そうです。カビが生えだすと、クリーニングが難しいので、もう天井板を張り替えないとならなくなり、費用が大きくかかってしまいます。病院の天井にカビというのは、衛生上きわめて不適切なので、そうなると早急な改修工事が避けられなくなります。おかしいと気づいたらすぐに対策を行なわないといけないと思います。
半田:どんな対策があるんでしょうか?
八島:一番簡単な方法は、天井内の空気を循環させることです。天井内に扇風機のようなファンを設置して、天井裏の空気を攪拌する方法です。次に試みるのは、天井内に廊下などの乾いた空気を吹き込む方法です。これも効果があります。ただ、病院では感染防止対策も重要なので、どの廊下から天井内に空気を入れるかは、慎重な検討が必要です。三つめは、天井内に除湿器を設置する方法です。前の二つに較べるとコストはアップしますが、一番効果が高い方法です。実際に、この方法を行った施設もすでにあります。
半田:結露って怖いんですね。国連が地球の温暖化を「地球が煮沸されている」と表現していましたが、これからの建築物は、そういう対策が急速に必要になってくるようですね。
半田:やはり夏場ですか?発生するのは窓ガラスなどでしょうか?
八島:発生時期はやはり夏場で、湿度と温度が上がりだす6月から9月にかけては要注意です。発生する場所ですが、最近の窓ガラスは2重ガラスになっているのが一般的なので、窓ガラスでの結露はあまり問題にはなりません。問題になるのは、天井裏とか、倉庫の中とか、空気が澱みやすい場所、普段あまり目に入らない場所で発生する結露です。
半田:そんなところが結露するんですか。
八島:天井裏は、特に要注意です。天井から水が落ちてきたので、配管などの漏水かと思って天井に入ってみると、天井板の上に水が溜まっていたという事故が確認されています。雨が漏るような場所ではないので、最初は判らなかったのですが、調べるうちに結露が原因だと判明しました。
半田:放っておくと、カビが生えてくるのではないですか?
八島:そうです。カビが生えだすと、クリーニングが難しいので、もう天井板を張り替えないとならなくなり、費用が大きくかかってしまいます。病院の天井にカビというのは、衛生上きわめて不適切なので、そうなると早急な改修工事が避けられなくなります。おかしいと気づいたらすぐに対策を行なわないといけないと思います。
半田:どんな対策があるんでしょうか?
八島:一番簡単な方法は、天井内の空気を循環させることです。天井内に扇風機のようなファンを設置して、天井裏の空気を攪拌する方法です。次に試みるのは、天井内に廊下などの乾いた空気を吹き込む方法です。これも効果があります。ただ、病院では感染防止対策も重要なので、どの廊下から天井内に空気を入れるかは、慎重な検討が必要です。三つめは、天井内に除湿器を設置する方法です。前の二つに較べるとコストはアップしますが、一番効果が高い方法です。実際に、この方法を行った施設もすでにあります。
半田:結露って怖いんですね。国連が地球の温暖化を「地球が煮沸されている」と表現していましたが、これからの建築物は、そういう対策が急速に必要になってくるようですね。
アフターコロナで変わったこと
半田:コロナウイルスが5類に引き下げられましたが、アフターコロナで病院づくりが変わってきたことはありますか?
八島:非接触化とゾーニングの徹底ですね。
半田:ちょっと難しい言葉ですが・・・
八島:非接触化というのは、文字通り触らないこと、つまり触らずに操作できるものが増えてきたということです。例を挙げると、自動ドア、自動水栓、センサーによる電灯のオンオフなどなど、中にはエレベーターの操作盤まで非接触にしたケースもあります。
半田:そういえば、最近トイレのドアが自動ドアだったことがありました。では、ゾーニングの徹底といいますと?
八島:院内のエリアを、微生物的にクリーンな場所と、少し汚染されている場所に明確に区別して、ヒトとモノの動線を管理することが徹底してきたということです。特に、病棟への入退出は、近年、非常に厳格化してきています。
半田:そういえば、病室へのお見舞いも、最近は管理が厳しいですよね。
八島:そうですね。患者さんの命と健康を守るため、私たち設計者も、これまで指摘されていなかったさまざまなリスクを予測して、設計する時代がやってきたと思います。
 非接触型のエレベーター操作盤
非接触型のエレベーター操作盤
八島:非接触化とゾーニングの徹底ですね。
半田:ちょっと難しい言葉ですが・・・
八島:非接触化というのは、文字通り触らないこと、つまり触らずに操作できるものが増えてきたということです。例を挙げると、自動ドア、自動水栓、センサーによる電灯のオンオフなどなど、中にはエレベーターの操作盤まで非接触にしたケースもあります。
半田:そういえば、最近トイレのドアが自動ドアだったことがありました。では、ゾーニングの徹底といいますと?
八島:院内のエリアを、微生物的にクリーンな場所と、少し汚染されている場所に明確に区別して、ヒトとモノの動線を管理することが徹底してきたということです。特に、病棟への入退出は、近年、非常に厳格化してきています。
半田:そういえば、病室へのお見舞いも、最近は管理が厳しいですよね。
八島:そうですね。患者さんの命と健康を守るため、私たち設計者も、これまで指摘されていなかったさまざまなリスクを予測して、設計する時代がやってきたと思います。
 非接触型のエレベーター操作盤
非接触型のエレベーター操作盤
この記事に関するお問い合わせはこちら